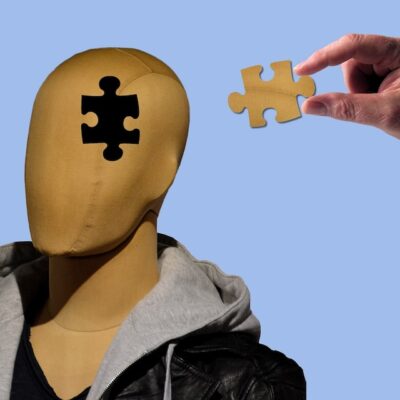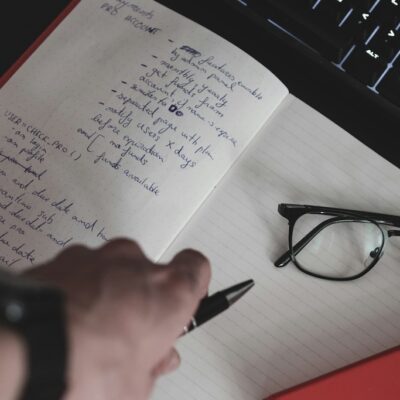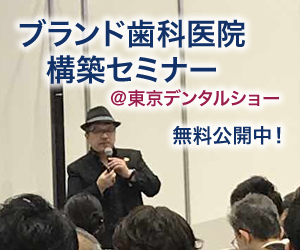「広告費だおれ」にならない!集患戦略の本質
先日、ある歯科医院の院長から
「ずっと自転車操業みたいな感じで楽にならない」
という相談を受けました。
よくよく話を聞いてみると、
新規患者は確かに来院しているのですが、
きちんと最後まで通院する患者も、メンテナンスや
定期健診、予防歯科などに継続通院する患者もごくわずか!
という現実が見えてきました。
これは「広告費だおれ」の典型的な事例です。
あなたの歯科医院は大丈夫ですか?
似たり寄ったりになっていないでしょうか?
集患のために広告を打ち、それなりに新患は来るのに、
医院の収益がなかなか増えない…
こうした状況に陥る最大の要因は、
集患戦略のバランスが取れていないことにあります。
広告は基本的に
「新規患者の獲得」のための施策を文字通り「広く告げて」
患者予備軍の方々との接点を増やす手法の一つに過ぎません。
しかし、多くの院長先生は
この「新規患者獲得」だけに注力してしまう傾向があります。
患者獲得を水汲みに例えるなら、
広告で新患を集めることはバケツに水を注ぐ行為です。
そのバケツに穴が開いていたらどうでしょう?
いくら水をたくさん注いでも
バケツはすぐに空になってしまいます。
歯科医院経営でこの「バケツの穴」にあたるのが
「既存患者の流出」と「中断・終了患者の放置」です。
集患戦略は大きく3つの柱で構成されます。
2つ目は「既存/通院患者の流出防止」
3つ目は「終了患者・中断患者の再来院促進」
この3つがバランスよく機能して
初めて安定した集患と医院経営が実現します。
実は私もせっかく開業した自分の歯科医院を
倒産寸前にした経験を持っています。
原因を分析した結果、患者は来院するものの
長期的なリピートにつながっていないことが判明したのです。
経営において最も重要なのは顧客生涯価値(LTV)です。
主訴だけ治療して来院しなくなる自由診療の患者よりも
保険診療でも長期的に通院し続ける患者の方が
医院にもたらす価値ははるかに大きいのです。
では、3つの集患戦略をバランスよく実践するためには
具体的にどうすればよいのでしょうか?
それぞれの施策について詳しく見ていきましょう。
効果的な集患施策の3つの柱
新規患者獲得のための施策
新規患者獲得は集患の入口として
確かに重要な施策です。
一般的な手法としては、チラシやウェブ広告、
看板設置、ホームページの充実などが挙げられます。
しかし、ただ闇雲に新しい手法に費用を投じるのではなく、
自院のポジショニングを明確にした上で、
ターゲット患者への接点が多い手法、気づきやすい手法に
優先的に資金を投下し、内容を充実させることが重要です。
たとえば、矯正治療に強みがあるなら
その特化型のコンテンツをホームページに充実させる。
インプラントを得意とするならその安全性や実績を強調する。
現在の歯科界の状況では「何でもできる歯科医院」よりも
「〇〇に強い歯科医院」の方が患者の関心を惹きやすいのです。
また、費用対効果の高い施策として紹介制度の充実も効果的です。
既存の患者からの紹介で来院する方は、初めから信頼関係の
土台ができているため好感度が高い傾向にあります。
「ご紹介カード」を用意するだけでなく、
紹介された患者と紹介者の双方に
メリットがある仕組みを作りましょう。
例えば、紹介者にはV.I.P患者として
新治療などのモニター参加権を与える。
紹介された患者には初診時の
検査料や相談料などを無料にするなどです。
さらに、地域活動への参加も
長期的に見れば効果的な新患獲得策です。
地域の健康イベントや学校での
歯科健診ボランティアなどを通じて
地域住民との接点を増やしましょう。
こうした活動は即効性はありませんが、
地域に根ざした歯科医院というブランドを
構築するのに役立ちます。
既存患者の流出を防ぐ施策
実は多くの歯科医院が見落としがちなのが
この「既存患者の流出防止」です。
新規患者の獲得に比べて
コストが低く効果が高いにもかかわらず、
重視されていないことが多いのです。
既存患者の流出を防ぐ第一の方法は
メンテナンスへの移行促進です。
治療が終わった後も定期的なクリーニングや
検診のために来院してもらう仕組みを作りましょう。
これには患者教育が欠かせません。多くの患者は
「痛みがなければ歯科医院に行く必要はない」
と考えています。
定期的なメンテナンスの重要性を
わかりやすく伝える工夫が必要です。
例えば、レントゲン写真や口腔内写真を
使って現状を視覚的に説明する。
歯周病の進行や虫歯のリスクを数値化して伝える。
こうした「見える化」によって
患者の理解と納得を得られます。
また、スタッフ全員による
「一貫したホスピタリティ」も重要な要素です。
患者の名前を覚え、
前回の会話や治療内容を引き継いだ対応をする。
待合室での快適さにも配慮する。
これらは些細なことのように見えますが
患者の「またこの歯科医院に来たい」という
気持ちを育てる上で非常に重要です。
さらに、予約のリマインドメール・電話や
院内ニュースレターの発行、
SNSでの情報発信なども効果的です。
特に最近では、歯の健康に関する
有益な情報をSNSで発信することで
患者との接点を維持している歯科医院が増えています。
中断・終了患者の再来院を促す施策
治療途中で来院しなくなった患者や
治療終了後に定期検診に来なくなった患者は、
実は大きな機会損失になってしまっています。
これらの患者は既にあなたの歯科医院を知っており、
一度は信頼して来院した方々な訳です。
新規患者獲得よりも少ない労力で
再来院につなげられる可能性が高いのです。
まず取り組むべきは連絡手段の多様化です。
電話だけでなく、メール、LINE、SMS等
患者の希望する連絡方法が使用可能な体制を整えましょう。
次に、リコールのシステム化が重要です。
最後の来院から3ヶ月、6ヶ月など一定期間経過した患者に
メッセージを送る自動化システムを導入する。
スタッフが個別に対応するのではなく
システムとして運用することで取りこぼしを防ぎます。
また、中断患者向けの特別キャンペーンも効果的です。
「久しぶりにお会いしたい」というメッセージを添えた
検診無料券やクリーニングの割引券を送付する。
季節の変わり目など、歯の健康について
考えるきっかけとなるタイミングを選ぶと効果的です。
さらに、患者をランク分けして
アプローチの優先順位をつけることも重要な戦略です。
過去の診療内容や頻度、反応履歴などから
再来院の可能性が高い患者から順に
働きかけていきましょう。
特に自由診療の提案に前向きだった患者や、
家族ぐるみで通院していた患者は優先度が高いです。
より良い明日のために
ここまで3つの集患施策についてお話ししてきましたが、
これらを効果的に機能させるためには土台が必要です。
それは「歯科医院としての明確な方向性」
と「それを支える組織のクオリティ」です。
現代の患者、特に意識の高い患者は
単に痛みを取り除くだけの治療では満足しません。
治療技術の高さは当然として
わかりやすい治療説明、メンテナンスの重要度の解説、
丁寧なコミュニケーション、心地よいホスピタリティなど
総合的な医療体験を求めています。
あなたの歯科医院は、患者に対して
どのような価値を提供したいですか?
どのような患者に来てほしいですか?
どのような歯科治療で問題解決をしたいですか?
これらの問いに明確に答えられることが
持続可能な集患戦略の第一歩です。
理想的には開業前から
院長自身の価値観や診療方針、経営哲学、志などを
明確化・言語化し、見合ったロケーション、設備、内装と
あなたに共感して共に進めるスタッフを揃えたいものです。
すでに開業している場合でも、今からでも遅くはありません。
まずは自分自身の価値観を見つめ直してみましょう。
そして、その価値観をスタッフと共有することが重要です。
院長とスタッフが同じ方向を向いて歩んでいける歯科医院では
患者への対応も自ずと一貫性が生まれます。
また、スタッフが主体的に
業務改善に取り組める環境づくりも欠かせません。
日々患者と接しているスタッフこそが
現場の課題を最もよく知っています。
定期的なミーティングでスタッフの意見を聞き、
改善提案を積極的に取り入れる姿勢が大切です。
人は仕事の意義を感じられると
モチベーションが高まります。
「この歯科医院で働く意味」を
スタッフ一人ひとりが感じられる
組織文化を育んでください。
最後に強調したいのは「ブランディング」の重要性です。
ブランディングとは単にロゴや内装を
洗練させることではありません。
あなたの歯科医院が大切にする価値観を
すべての接点で一貫して表現し続けることです。
集患施策も、このブランディングの一部と捉えることで
初めて本当の効果を発揮します。
今日からでも、あなたの歯科医院の
集患戦略を見直してみませんか?
「広告費だおれ」から脱却し、持続可能な成長への
第一歩を踏み出しましょう。