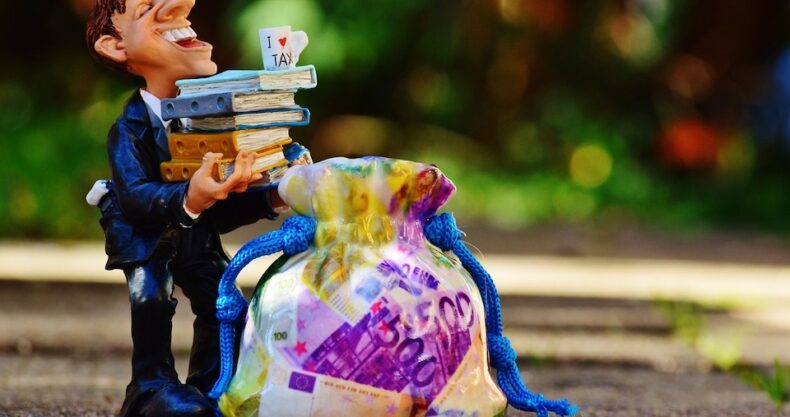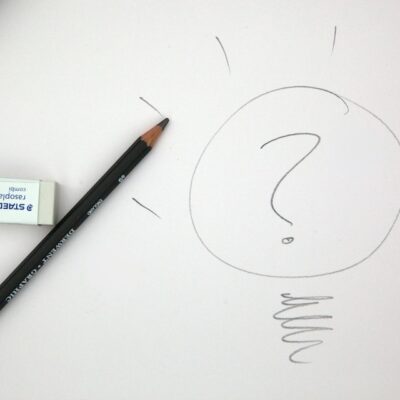年末の慌てない歯科医院経営 – 収入管理の考え方
先日、ある書店で面白い光景を目にしました。
私はいわゆる”本の虫”なので、書店をよく訪れます。
今年もあと2ヶ月足らずですが、
年末になると結構見慣れた光景に出会います。
それは、書籍を10冊近くまとめ買いする
方々が書店内を行き来する姿です。
「今年も経費の予算を使い切らないと…」
ということなのでしょう。
私は内心、ついつい苦笑してしまいます。
ですかこれと同じようなことが、
多くの歯科医院で行われています。
ただし目指しているのは”予算の消化”ではなく
”租税特別措置法26条”適用のための収入削減です。
節税のために「あえて」行う行為である点は共通です。
措置法第26条は経費の計上に関する特例で、
実際の経費ではなく概算で経費計算ができる制度です。この制度を利用すると
実際にかかった経費以上の経費計上が可能で、
課税所得の減額ができます。
歯科医業にかかる総収入金額が7,000万円以下、
かつ社会保険診療報酬が5,000万円以下。
これが適用条件となっています。
12月になって、社会保険診療報酬が5000万円、
または自由診療を含む総収入が
7000万円を超えそうになると、あわてて年末に
休診日を増やしたり、予約を制限したりする…
こんな歯科医院が後をたちません。
あなたにはこのような経験はありませんか?
租税特別措置法26条の適用は、
歯科医院経営者に与えられた権利ですので、
適応条件を満たしているなら堂々と
適応した節税されると良いでしょう。
しかし、年末になって慌てふためくのは
百害あって一利なし!
少なくとも感心はできません。
この「年末あわて症候群」は、実は
歯科医院経営における典型的な
「後手対応」の表れなのです。
歯科医師として優れた臨床スキルを持つ先生でも、
経営面では「痛みが出てから」対処する
習慣が身についていることがあります。
患者の口腔内を定期的に検診して予防するように、
歯科医院の経営状態も定期的に確認し、
先を見越した対策を講じることが大切です。
これから私がお伝えする内容は、
単なる税務対策ではありません。
あなたの歯科医院が安定した経営基盤を築き、
ストレスなく診療に集中できる環境を
作るための考え方です。
後手に回る収入管理とその影響
先日、ある歯科医院の院長先生から
こんな相談を受けました。
近づいている』と言われました。どうすれば…」
残念ながら、この対処は明らかに遅すぎます。
特別措置法の限度額に近づいているかどうかは、
12月を待たずとも把握できるからです。
先生の歯科医院では、毎月の収入状況を
きちんと確認していますか?
半年が経過する6月時点、もしくは遅くとも
9月の時点で年間の収入予測を立てれば、
余裕を持った対応が可能なのです。
ある歯科医院では、7月の時点で
このままでは年間社会保険診療報酬が
5200万円に達する見込みとわかり、
計画的に収入調整を行いました。
結果、12月に慌てることなく、
租税特別措置法26条の適用可能な状態を保ちながら
診療を続けることができたのです。
対照的に、別の歯科医院では繁忙期の年末に急遽、
休診日を増やしたため、患者からの不満が相次ぎ、
信頼低下と自由診療の低迷いう二次被害まで発生しました。
歯科医院経営における最大の失敗は
「対処が可能な時期に行動しないこと」です。
いわば、初期のカリエスを放置して
結果として根管治療が必要になるようなものです。
また、収入管理を後回しにする理由として
「数字を見るのが苦手」
とおっしゃる先生も少なくありません。
しかし、複雑な根管治療を
成功させる技術を持つ先生が、
簡単な収支確認を出来ないはずがないのです。
必要なのは習慣化だけです。
毎月の収支と年初からの累計収入を
確認する15分の時間が、年末の大きな
混乱を防ぐことにつながるのです。
収入を適切にコントロールする
収入が措置法の限度額に近づいていることが
わかったとき、どのような対策が
考えられるでしょうか?
ここでは歯科医師自身が無理なく
実践できる方法から順に紹介します。
対策1. 診療内容の微調整
最も手軽なのは、診療ペースのわずかな調整です。
多くの歯科医院で採用している”15分に1人”の予約を
”20分に1人”に延ばします。
診療時間を5分延ばすだけですがその結果、
1時間での診療人数は4人→3人となり、
1日の患者数を自然に調整できます。
1日の診療時間が8時間なら、
この施策で1日の患者数を8人減少できます。
「8人減はちょっと…」というなら
1時間3人枠と4人枠を交互に並べて
1日4人減というやり方もあります。
元々患者のアポが入りにくい時間帯だけの実施では
1日の患者数の減少が少ない=収入が減少しないなら
他の時間帯も…というように柔軟に対応できます。
延ばした診療時間に患者との対話に当てることで、
患者の満足度向上に繋げることが可能です。
この施策を実践したある院長先生は、
問診や説明時間を充実させたことで
患者からの評価と信頼度が高まりました。
もう一つの効果的な方法は、1回の診療で
行っていた治療の進捗を2回に分けることです。
間接法で作成したコアのセットと、
歯冠形成・印象を同日に行っているなら、
それを2回の診療日に分けるといった工夫です。
これによって診療1回あたりの患者負担単価が
下がるだけでなく、患者の体力的な負担も
軽減されるメリットがあります。
対策2. 計画的な研修・セミナー参加
10月や11月に宿泊を伴うセミナーに
参加するために休診日を設けることも効果的な調整手段です。
スタッフには有給休暇として処理すれば不満も生じません。
研鑽のための休診なら患者からの理解も得やすいでしょう。
対策3. スタッフ研修や社員旅行の実施
年末の忙しい時期を避けて10月や11月に
スタッフ研修や社員旅行を実施することも悪くありません。
チームビルディングと収入調整を同時に達成できます。
ある歯科医院では、11月に2日間の
チーム研修を行い、収入調整はもちろん、
結果的にスタッフのモチベーション向上に成功しました。
重要なのは、これらの調整を
突然導入するのではなく、計画的に実施することです。
特に年末急遽の休診増加は、患者の信頼を
損なう可能性が高いため避けるべきです。
損益分岐点による判断
社会保険診療報酬が5000万円、または総収入が
7000万円をほんの少しだけ超える見込みの場合、
収入を調整して両方とも限度額以下に抑え、
租税特別措置法の適用を受けた方が
有利なケースが多いのです。
問題は、収入予測で以下のケースが
見込まれる場合です。
総収入は7000万円未満になる
②社会保険診療報酬は5000万円未満だが、
総収入が7000万円を超える
③両方とも上限を超える
このいずれかになりそうだと確認した時点で、
このまま推移すれば経費計算に
特別措置法は適用できず、実費計算になります。
この段階で検討すべきなのは、
収入調整をして租税特別措置法の適用を受けるか、
このまま実費計算にするかという選択です。
どちらが有利かは、経費率を含めて
年末時点の収入予測をシミュレーションし、
税引後利益で比較する必要があります。
一般的に、措置法適用なら経費は少ない方が
税引後利益は増えます。
一方、実費計算では経費増大で税金は
抑えられますが、税引後利益も減ります。
繰り返しますが、限度額をわずかに超える程度なら、
「収入調整で措置法適用」が有利な可能性が高まります。
あくまで可能性であることには注意してください。
あなたの歯科医院の具体的な数字に基づく
検証が必要ですので、定期的な数値チェックを
欠かさないようにしましょう。
先を見越した歯科医院経営を
これまでお伝えしてきた内容は、
単なる税金対策ではありません。
先を見越した計画的な収入管理は、
あなたの歯科医院経営全体の質を
高めることにつながります。
収入調整のために行う患者との対話時間の増加や
治療計画の丁寧な見直しは、
結果的に患者満足度の向上をもたらします。
スタッフ研修や自己研鑽のための時間確保も、
中長期的な歯科医院の価値向上に
直結するものです。
最も大切なのは、これらの取り組みを
PDCAサイクルにのせることです。
毎月の収支確認→年間予測→対策立案→実行→効果確認
というサイクルを習慣化しましょう。
具体的には、今日から以下の3つの
アクションを始めてみてください。
2. 四半期ごとに年間収入の予測を立てる
3. 半期ごとに収入調整策のメニューを更新する
これらの習慣が、あなたの歯科医院を
「いつも年末に慌てる医院」から
「計画的に成長する医院」へと変えていきます。
そして何より、あなた自身が
診療に集中できる時間的・精神的余裕を
手に入れることができるのです。