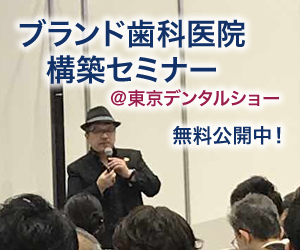先生、毎日の診療、本当にお疲れ様です。
こんにちは、株式会社120パーセント代表、
ニッチな自由診療でも「先生のその治療が受けたい!」患者が集まる歯科医院構築、
クリニックの経営アドバイザーで歯科医師の 近 義武 です。
前を通る通行人に先生の歯科医院は認知されてる?
「歯医者に行くこと」は、多くの人にとってはちょっと勇気が入ります。
どんな先生だろう?、痛くないかな?、院内は清潔かな?
なんて、患者はたくさんの不安を抱えているものです。
特に患者にとって、初めての歯科医院ならなおさら。
院内の雰囲気や治療方針、そういった情報を少しでも
事前に知ることができれば、不安はグッと軽くなるはずです。
「いやいや、うちはちゃんとホームページを用意していますよ」
という声が聞こえてきそうですね。素晴らしいことです。
今の時代、ホームページは歯科医院の顔ですから。
では、そんな先生に質問です。
「あなたの歯科医院の前を毎日、何人が通り過ぎているでしょうか?」
「そして、その人たちを、先生の歯科医院のホームページに誘導する
具体的な仕掛けを、何か実践されているでしょうか?」
「え、そこまで必要なの?」と思われたかもしれません。
ですが、ここが非常に重要なポイントです。
どんなに立派なホームページも、
見てもらえなければ存在しないのと同じなのです。
この記事では、歯科医院の前を通る「患者未満の通行人」に
どう気づいてもらい、ホームページへスムーズに導くか、
その具体的な方法をお伝えします。
患者とは、ここが最初の、そして重要な接点=コンタクトポイントなのです。
なぜ、あなたの歯科医院のHPは素通りされるのか?
先生の歯科医院の前には、毎日たくさんの人が行き交っています。
それなのに、ホームページまではたどり着いてもらえない…
一生懸命作ったホームページが、まるで存在しないかのように
素通りされてしまうのは、一体どうしてなのでしょうか?
その理由を、これから一緒に深く掘り下げて考えていきましょう。
実は、そこには見過ごせない”落とし穴”があるのです。
“見てくれるはず”という思い込み
院長先生とお話ししていると、大部分の先生が
「うちは治療の質に自信がある」
「ホームページも専門業者に頼んでしっかり作った」
と、胸を張られます。それは本当に素晴らしいことです。
でも、ここで一度立ち止まって考えてみてほしいのです。
その素晴らしい歯科医院のホームページ、
本当に「見てもらえる」と確信していますか?
患者は仮に関心があっても、そんなに手間をかけてくれません。
歯科医院のHPは、推し活中のアイドルのサイトではないのです。
更新を待ち望んだり、隅々まで読み込んだりなんて期待するだけ無駄です。
たとえば、先生の歯科医院の前を
偶然通りかかった人がいたとしましょう。
その人が、ふと看板を見て、
「お、ここに歯医者があるな」と認識したとします。
では、その人が家に帰ってから、
わざわざ先生の歯科医院名を検索窓に打ち込んで、
あなたの渾身のホームページを探し出すでしょうか?
よほどの事情や切実な悩みを抱えている人でもない限り、
そんな面倒なことはしないのが普通で当たり前です。
現代は情報過多の時代。
「ちょっと気になる」程度では、人はなかなか行動に移しません。
「ウチは看板にQRコードを貼っているから…」
それも一つの手ですが、それだけでは効果は薄いでしょう。
なぜなら、患者にとって「そのQRコードを読み取るメリット」が
明確に伝わっていなければ、スマホをかざす手間すら惜しむからです。
そして、もう一つ、もっと厳しい現実があります。
それは、”そもそも関心を持たれない”ということです。
悲しいかな、多くの人にとっての歯科医院は、
・痛くなったら行く場所
・できればあまり近づきたくない場所
というネガティブなイメージが先行しがちです。
日常生活の中で、積極的に
「どこか良い歯医者ないかな~」と探している人は、
実は極々少数派なのです。
たとえば、近所にイタリアンレストランがオープンしたら、
「どんなお店かな?」と興味本位で調べる人もいるでしょう。
でも、それが歯科医院だったらどうでしょう?
「ふーん、歯医者か」で終わってしまうのが関の山です。
つまり、先生方が思っている以上に、
一般の人は歯科医院に対して「無関心」なのです。
ここをしっかり認識しないと、優れた診療を提供して、
それを良いHPでアピールすれば、いつか誰かが見てくれるはず!
という、淡い期待だけで終わってしまいます。
先生の歯科医院の良さ、こだわり、診療に対する誠実さなどを
それを知らない人にどうやって届けるか?
まずは、この「思い込み」と「現実のギャップ」を
直視することから始めなければなりません。
通行人にスマホをかざさせる“きっかけ”作り
さて、ここまでは「ホームページが見られない厳しい現実」
についてお話ししました。
「じゃあ、どうすればいいんだ!」という声が聞こえてきそうですね。
大丈夫です。今からでもできることは、たくさんあります。
大切なのは、これまでの「待ち」の姿勢から、
積極的に「仕掛ける」姿勢へと意識を切り替えることです。
では、具体的にどんな“きっかけ”を作ればいいのでしょうか?
いくつかアイデアをお伝えしましょう。
1.ファサード掲示で「おっ?」と思わせる
歯科医院の入口や窓、袖看板などを総じてファサードと呼びます。
先生の歯科医院では、ここに何を掲示していますか?
診療時間や休診日だけ、なんてことはありませんよね?
たとえば、道行く人が思わず足を止めてしまうような、
そんな”患者にとっての価値”を一目でわかるように打ち出します。
例えば、
ウチの子の歯並び、大丈夫?
“子どもの歯並び相談(無料)”受付中!
白い歯、諦めていませんか?
おウチでできるホワイトニング、お気軽にご相談を!」
“院長おすすめ!歯周病セルフチェックリスト”
こちらのリーフレットをご自由にお取りください!
よくある街のパン屋さんが、美味しそうなパンの写真と
手書きPOPで食欲をかき立てるように、先生の歯科医院も
「患者がちょっと気になりそうな」情報を発信するのです。
2.QRコードは「読み取る理由」をセットに
「QRコード、設置はしてるけど誰も読み取らないよ…」
という先生、多いんじゃないでしょうか?
それは、患者に”そのQRコードを読み取る明確なメリット”が
明確に伝わっていないからです。
ただ「ホームページはこちらから」では弱いのです。
読み取った先にどんな有益な情報があるのか、
それを具体的に示すことが大切です。
例えば、
当院の”痛みを小さく抑える治療への3つの工夫”
今すぐこちらでチェック!(QRコード)
初めての方へ。院長の診療への想いと
院内紹介ツアーの動画はこちらから(QRコード)
今月の健康コラム:『マスク生活と口呼吸の意外な関係』
こちらで全文読めます」(QRコード)
人は「自分に関係がある」「得をする」と思わなければ行動しません。
通行人全員の関係があることや、得することはほとんどありません。
誰に情報を受け取って欲しいのか、誰の得になるのかを
十分に考慮しなくては、効果は限定的になるので注意しましょう。
3、HPの「チラ見せ」で期待感を高める
先生のHPには、素晴らしい情報が詰まっているはずです。
その一部を、ファサードで“チラ見せ”する手があります。
あなたの歯科医院の自慢できることや
他の歯科医院とはちょっと違うことなどの
さわりの部分だけを見せていきます。
例えば、
小さな虫歯も見逃さない!”3つの診査機器”
治療か、経過観察かも判定可能「詳しくはこちら」
笑顔が素敵な当院スタッフの日常はこちら!
(写真と共に)スタッフの勤務風景を公開中です
ここで重要なのは完璧を目指さないことです。
まずは1つ「これならできそう」なものから試してください。
通行人の反応を観察し、効果がなければ別の方法を試しましょう。
これらの“きっかけ”作りは、
何も莫大な費用がかかるわけではありません。
患者視点を持ち、ちょっとした工夫をすることで、
今まで素通りしていた人が足を止め、
スマホをかざしてくれる可能性がグッと高まるはずです。
今日の“小さな一歩”が、明日の新患獲得に
ここまで、歯科医院の前を通る「患者未満の通行人」に
いかにして気づいてもらい、ホームページへと誘導するか、
その具体的な方法についてお話ししてきました。
立派なホームページを用意するだけでは不十分です。
通行人の足を止め、興味を持たせる「きっかけ」を
歯科医院側が意識して作っていく必要があるのです。
ファサード掲示の工夫、QRコードの戦略的な活用、
そして何よりも大切なのは、
「患者は何を知りたいのか?」
という視点を持つことです。
結局のところ”意識の転換”、すなわち
「待ち」の姿勢から「仕掛ける」姿勢への転換が必要!
「いろいろ言われたけど、何から手をつければ…」
そう思われた先生もいらっしゃるかもしれませんね。
難しく考える必要はありません。
まずは、この記事でお話ししたアイデアの中から、
たった一つで良いので、試してみてください。
例えば、明日の朝、診療を始める前に、
一度、ご自身の歯科医院のドアから一歩外へ出て、
初めて来た患者のつもりで、看板や入口周りを眺めてみる…
それだけでも、何か新しい発見があるはずです。
今日蒔いた小さな種が、明日すぐ芽を出すとは限りません。
しかし、何もしなければ、何も変わらないのです。
その小さな一歩、その小さな改善の積み重ねが、
気づけば大きな変化となり、新患を引き寄せるのです。
それはまるで、ドミノの最初の牌をそっと押すようなもの…
先生の歯科医院には、必ず光る魅力があるはずです。
それを、まだ知らない多くの人に届けるために、
今日からできることを始めてみませんか?
先生方のそうした前向きな努力は何らかの形で必ずが実を結びますよ。