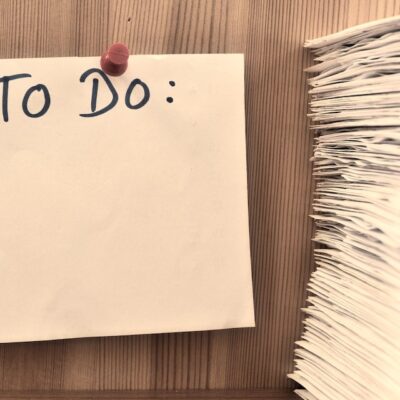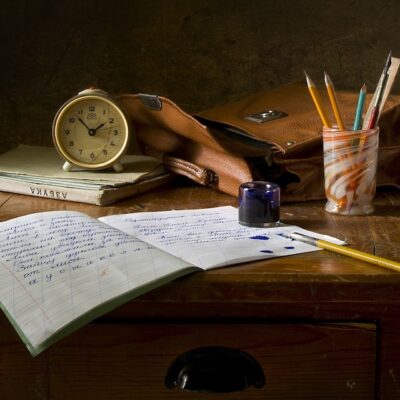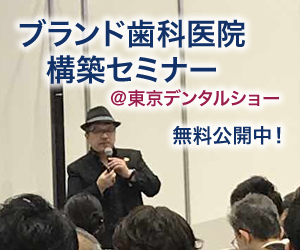患者目線を失った歯科医師の盲点
先週、友人のスマートフォン購入に
付き添う機会がありました。
店員さんは新製品の性能について
「最新のプロセッサー搭載」
「4,800万画素のカメラ」
「8K動画撮影可能」
と熱心に説明。
しかし友人が最終的に選んだのは
スペックではやや劣る機種でした。
理由を聞くと「バッテリーが長持ちする」
「手に馴染むサイズ感」
「使いやすいインターフェース」だと言います。
ここに専門家と一般ユーザーの視点の違いが
はっきりと現れていました。
専門家は「性能や機能」を重視しますが、
ユーザーは「日常での使いやすさ」を
何より大切にしているのです。
この光景を見て、私は歯科医院の
経営課題と重なるものを感じました。
あなたも診療中には、患者のことを
全力で考えているはずです。
痛みを最小限に抑えるよう心がけ、
最適な治療方法を選択する。
そして治療結果には
医療人としての誇りを持っている。
しかし、集患やマーケティングとなると
どうでしょうか?
「CTによる精密診断が可能」
「マイクロスコープを使用した根管治療」
このような宣伝文句は、
患者目線に立てていない典型例なのですが、
どこの何がマズいのか、お分かりになるでしょうか?
治療も集患も本質は同じです。
「相手の目線に立ち、何ができるか?」
これを真剣に考えること。
「そうだよな」と思われたでしょう。
当然自分では患者目線で集患施策が
行えていると確信もしているでしょう。
ところが現実は厳しいものです。
いざ集患やマーケティングの施策が
実際に形になってみると、
(自分はできていると信じていますが)
患者目線には程遠くなりがちです。
なぜ、こんなことが起こるのでしょうか?
患者目線で見ることが出来ない
その理由は、意外なほど単純です。
もはや患者としての思考ができない!
そんな体、そんな脳になってしまっているのです。
考えてみてください。
あなたは何年もの間、専門的な歯科医学を学び、
日々臨床経験を積んできました。
その過程で、口腔内の状態を見れば
瞬時に問題点が把握できるようになり、
専門用語を日常会話のように使えてもいます。
これ自体は素晴らしい医療技術者としての成長です。
しかし、この成長が皮肉にも
「患者目線」を失わせる原因となっているのです。
例えば、あなたは「根管治療」という言葉を聞いて
何を連想するでしょうか?
治療手順、使用器具、麻酔使用の正否、
根幹長の測定、レントゲン撮影、投薬のレシピ、
起こりうるアクシデントや解決方法…
際限なくさまざまなことが、脳内を駆け巡るはずです。
歯科医師にとっては日常茶飯事で、
特に意識することもないことでしょう。
たった一言「根管治療」というワードから、
これらのことが想起される脳になっているのです。
「根管治療」を
『神経の治療』『歯の根っこの治療』と言い換えても
患者があなたと同じように反応するはずがありません。
せいぜいが昔の受診経験を思い出して
場合によっては不安と恐怖を呼び起こして
ネガティブな気分になるのが関の山。
こんなにも脳の構造が違ってしまっているのです。
その結果、
「十分に患者目線でわかりやすくできた!」
と思っている集患やマーケティングの施策が、
患者に微塵も刺さらないという事態が多発します。
ある歯科医院では、
最新の「Er:YAGレーザー導入」を
全面に押し出した広告を出しました。
院長は「患者に最先端の治療を提供できる」
と胸を張っていましたが、
新患はそれほど増えませんでした。
なぜでしょう?
患者が求めていたのは
・痛みはどうなのか
・すぐに治るのか
・再治療にならないのか
・永く保つのか
・高額になるのか
このような「自分に直接関係していて、
理解ができる変化、効能、値段」などです。
正直、治療の方法や最先端技術かどうかなど
二の次、三の次のことなのです。
この認識のズレは歯科医師である以上、
自覚することがとても難しいものです。
自分自身の思考の癖を客観的に把握し、
”歯科医師脳”を意図的にshut offして
物事を眺める訓練など誰もやらないからです。
ですから、マーケティングや集患がうまくいかないと
「広告会社の実力不足」
「スタッフの説明不足」など、
自分以外の他者が原因と考えがちです。
このような思考の偏りを
「専門家バイアス」と呼んだりしますが、
これはあなただけの問題ではありません。
歯科医師であるあなたの脳は、すでに
「専門家の思考」に改造されているのです。
歯科医師だけの問題ではない
実はこの「専門家バイアス」、
歯科医師だけに限った話ではありません。
情報の非対称性がある業種なら、
多かれ少なかれ発生する普遍的な問題です。
建築家は構造美や素材の特性を語りますが、
住む人は「使い勝手」や「居心地」を重視します。
IT技術者は最新技術を誇りますが、ユーザーは
「シンプルで使いやすい」ことを求めています。
料理人は素材の質や調理技術にこだわりますが、
食べる人は「おいしい」体験を大切にしています。
これらはすべて
「専門家と一般人の認知ギャップ」の表れです。
このギャップを完全に埋めることは、
残念ながら不可能です。
なぜなら、自分の専門知識を一時的にでも
「忘れる」ことは極めて困難だからです。
自らチェックするためには、
相当な負荷を脳にかけないといけません。
染み込んだ歯科医学の知識が
常に思考を邪魔するのですから。
患者目線を取り戻す
では、どうすれば患者目線を
取り戻すことができるのでしょうか?
あなた自身が患者目線を取り戻す方法としては
難しいことを承知で長年、訓練を続けるしかありません。
ただ、今すぐ患者目線の
マーケティングや集患施策を行いたいなら
その最も効果的な方法は、
適切な第三者の目を活用することになります。
他者にチェックを依頼するなら、
次のような人を選びましょう。
まず、この「専門家バイアス」と
闘い慣れている歯科医師です。
自分自身の専門知識を一時的に
「棚の上に上げておく」能力を鍛えつつ
患者目線の情報発信を継続している方の中から
ピックアップすると良いでしょう。
次の候補としては、生物学や医学の基礎知識があり、
マーケティングにも詳しい知識人です。
専門知識と一般視点の「翻訳者」として
貴重な存在になってくれるでしょう。
しかし注意点があります。
この能力は個人の資質に大きく左右されます。
肩書きや経歴だけで判断せず、
本人に直接会って観察してから判断しましょう。
また、一般の患者さんの意見を聞いてみることは重要ですが、
マーケティングや集患施策の評価者としては限定的でしょう。
彼らは「わかりやすさ」や「受け取りやすさ」は
評価できますが、マーケティング的な改善点までは
指摘できないことが多いからです。
最も大切なのは、
「あなた自身が専門家バイアスを持っている」
という自覚を持つことです。
その上で、日々の診療やカウンセリングで
「この説明は患者に核心が伝わるのか?」と
問い続けることが大切です。
患者目線が増患につながる
患者目線を取り戻すことは、
単なる倫理的な問題ではありません。
これは歯科医院経営において
直接的に増患と売上向上につながる重要戦略です。
なぜなら、患者が求めているのは
「技術的に素晴らしい治療」ではなく、
「信頼できる歯科医院・先生・スタッフ」
だからです。
患者の中には、自分の悩みが
自分でもよくわかっていない人や、
歯科なのか、別の科なのか不明な方もおいでです。
そういう方は、歯科医師やスタッフが信頼できて
話を聞いてくれると分かるまで
悩みがあっても打ち明けないことが多々あります。
患者の「本当の悩み」を解決することが出来たなら、
それは、リピート率向上と紹介増加の
最短ルートとなる可能性が爆上がりするということです。
明日から実践できるアクションとして、次の3つを提案します。
1. 医院のウェブサイトやパンフレット
その他、患者との接点となるポイントを洗い出し、
それぞれを患者視点で見直してみましょう。
あなたが患者視点に不慣れで自信がないなら
第三者を探して、評価、アドバイスを受けましょう。
改善を重ねてPDCAサイクルを回すことが大切です。
改善は1箇所ずつ、結果の測定実行は必須です。
2. 新しいサービスや設備導入に際して
「患者にとってのメリット」を必ず明確化・言語化する。
『何でも噛める』では患者目線のメリットではない。
『何でも噛める』ようになった際の患者の生活や感情の変化、
周囲からの評価、出来なかったことができるようになるなら
その楽しさや嬉しさまで踏み込むこと。
3. 患者からの質問や不安を記録する
共通する悩みをマーケティングに活かす。
その質問の奥に隠れた悩みは何か?
事前に不安を解消するにはどうしたら良いか?
それらを患者にどう伝えればわかってもらえるか?
愚直に質問や不安を収集して
訴える患者が多いほど丁寧に、大きなボリュームで
患者の目に触れやすい複数の媒体で答える。
このような「患者目線で見る」という
シンプルな姿勢の転換が、あなたの歯科医院を
選ばれる医院へと変える第一歩になるのです。