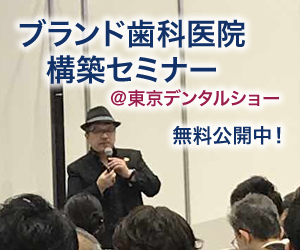信頼構築と経営安定の鍵を眠らせていませんか?
先日、あるレストランを訪れた時のことです。
「前回ご来店時にお聞きした、お好みのワインが入荷しました」
と、店員が声をかけてきました。
さらに「お連れ様は確か苦手な食材をお持ちでしたね」
と細やかな配慮も。
たかだか年2回程度の来店なのに、こんなに覚えてくれている。
この体験は、私に深い感動と同時に「なるほど!」という
気づきをもたらしました。
歯科医院の経営も、実はこれと同じなのです。
患者との会話から得られる有益な情報を、
あなたの歯科医院ではどれだけ活用できていますか?
多くの院長先生は、治療に関する情報だけを重視しがちです。
「ポケットの深さ」
「咬合の状態」etc.
こうした医療情報は確かに大切ですが、
治療以外の患者情報も、医院経営を大きく変える力を持っています。
「休暇の予定」「好きな話題」…
こうした情報の活用が、単なる「行きつけの歯科医院」から
「絶対に通い続けたい医院」へと患者の意識を変えるのです。
私が経営改善を依頼された歯科医院の多くは、
患者情報の活用が不十分なまま、
低い再診率やリコール率、紹介率に悩んでいました。
しかし、この「見えない資産」を活用し始めた結果、
院内の雰囲気は劇的に変わったのです。
この記事では、患者情報の効果的な収集・活用法と、
それがもたらす驚くべき恩恵についてお伝えします。
なぜ患者情報が医院経営の要なのか
「患者のことを歯科医院側がよく知っている」
これだけで医院の評価は大きく変わります。
患者情報を活用する最も大きな効能は、
信頼獲得とファン化の促進にあります。
たとえば、次のような場面を想像してみてください。
「○○さん、先日の甲子園の決勝、
応援していた高校が勝ってよかったですね!」
「お話していた海外出張、無事に終わりましたか?」
こうした何気ない声かけが、患者の心を掴むのです。
単に「歯を治してくれる場所」ではなく
「自分を覚えていてくれる場所」という認識の違いは絶大です。
数値で見ると、患者情報を適切に活用している
医院では、リコール率が平均20%も高くなっています。
また、自費診療の提案に対する成約率も
約30%高まるというデータもあります。
なぜでしょうか?
それは「この先生は自分のことを理解してくれている」
という安心感が、医療行為への信頼も高めるからです。
ある歯科医院では、患者情報の活用を徹底した結果、
紹介患者が前年比で2倍にまで増加しました。
この医院の院長は
「治療の腕前以上に、患者理解が鍵だった」と語ります。
患者は多くの場合、痛みや不安、恐怖といった
ネガティブな感情を抱えています。
そんな時、患者が
「この医院は自分のことを理解してくれている」
と感じられれば、その不安は大きく軽減されるのです。
そして、この安心感こそが、
再来院率を高め、治療提案の成約度を
向上させる最大の要因となります。
患者情報の活用は、単なるホスピタリティではなく、
経営の根幹を支える戦略的アプローチなのです。
治療技術を磨くことと同じくらい、
いや、それ以上に投資する価値のある
経営資源だと言えるでしょう。
患者情報共有の現状と課題
患者情報の収集・共有方法は、
歯科医院によって実に様々です。
コミュニケーションシート、サブカルテ、
パーソナルシート…呼び方も形式も千差万別。
運用方法も、カルテにコピー用紙を挟む医院、
衛生士の個人メモに頼る医院、
電子カルテのコメント欄を活用する医院、
レセコンにサブカルテ機能を追加している医院など、
それぞれ工夫を凝らしています。
しかし、形式や呼び方の問題ではありません。
本当に重要なのは、例えば患者Aさんと
接点を持つ可能性のあるドクター・スタッフ全員が、
その情報を共有できているかどうかです。
「先月話していた転職の件、どうなったんだろう?」
こうした情報を衛生士だけが知っていても、
院長である先生が知らなければ、
せっかくの信頼構築のチャンスを逃してしまいます。
実際、この情報活用を経営施策として進める際に
最も多く見られる課題がこの「情報の分断」です。
受付スタッフは患者の仕事の悩みを知っていても、
診療室のドクターには伝わっていない…
これでは、せっかく収集した貴重な情報が活きません。
中には「スタッフの脳内だけ」という医院もあります。
当然、担当者が休みの日には情報は活用不能、
さらに退職した後には、情報は完全に失われてしまいます。
また、「収集する情報に一貫性がない」という
問題も珍しくありません。
あるスタッフは趣味の情報を集め、
別のスタッフは家族構成を重視する…
こうしたバラバラな情報収集では、
患者理解の全体像が見えてきません。
ある医院では、朝礼時に「今日来院予定の患者の
個人情報」を共有する時間を設けたところ、
患者満足度が大幅に向上しました。
別の医院では、電子カルテとは別に
「患者情報データベース」を構築し、
誰でも簡単にアクセスできる環境を整えています。
重要なのは、システムの複雑さではなく、
「全員が確実に情報にアクセスできる」という原則です。
患者情報の収集・共有において最も大切なのは、
「システム化」と「標準化」なのです。
患者情報を活かした信頼関係構築
では、具体的にどのように患者情報を活用して
信頼関係を構築していけばよいのでしょうか。
まず大切なのは、情報収集の「型」を決めておくことです。
私がお勧めしているのは、次の5つの視点です。
②職業詳細(具体的な仕事内容、勤務形態)
③趣味・関心事(スポーツ、旅行、読書など)
④通院に関する事情(来院手段、所要時間)
⑤特別なイベント(昇進、引っ越し、記念日など)
これらの情報を、全スタッフがアクセスできる
統一フォーマットで記録します。
電子カルテなら専用フィールドを設け、
紙カルテならカラーの専用シートを
挟み込むなどの工夫が効果的です。
次に重要なのが「情報の更新と活用」です。
患者が来院するたびに、前回の情報を確認し、
自然な会話の中で新しい情報を引き出します。
「先日お話しされていた社内プロジェクト、
うまく進んでいますか?」
このような問いかけから始まる会話で、
患者はあなたの医院に特別な親近感を抱き始めます。
特に効果的なのは、治療の合間や、
治療後の短い時間を活用することです。
たった30秒の会話でも、
患者の心に残る印象は大きく変わります。
情報収集の際は、「聞き出す」のではなく
「自然な会話の中で知る」という姿勢が重要です。
「プライベートについて教えてください」
と質問するのではなく、
「今週末は天気が良さそうですね、
週末はどこかにお出かけの予定はありますか?」
といった自然な会話から始めましょう。
そして最も効果的なのが、収集した情報を
治療提案に活かす方法です。
例えば、海外出張が多い患者には
「出張中のトラブルを避けるための予防処置」として、
より高度な予防プログラムを提案できます。
スポーツ選手には「パフォーマンス向上」
という視点からマウスガードの提案が可能です。
こうしたパーソナライズされた提案は、
単なる「治療」から「あなたのための解決策」へと
患者の認識を変えます。
このサイクルを継続することで、
患者との関係は単なる「医師と患者」から
「人生のパートナー」へと深化していくのです。
情報活用で生まれる理想の歯科医院
患者情報を効果的に活用した歯科医院には、
どのような変化が訪れるのでしょうか。
最も大きな変化は、患者との関係性の質です。
適切に情報を活用して構築された関係は、
よほどのことがない限り瓦解することがありません。
こうした患者は、あなたの歯科医院の
信奉者的な存在となり、通院を継続します。
彼らは自然と院内の雰囲気を明るく活気あるものにし、
さらには知人や家族を紹介してくれる
超VIP患者へと成長していきます。
ある医院では、このような患者が全体の15%を
超えたところから、紹介率が飛躍的に向上。
新規患者の獲得コストが
3分の1に減少した例もあります。
この変化は経営数字にも直結します。
情報活用を徹底した医院では、
リコール率が平均30%上昇し、
自費率も1.5倍になるケースが珍しくありません。
そして何より、院長である先生自身の
歯科医師としての生活が変わります。
「今日も充実した診療と心地よい会話が待っている!」
という期待感を持って仕事に臨めるようになります。
スタッフも単調なだけの業務から解放され、
患者との豊かなコミュニケーションに
やりがいを見出すようになります。
患者に頼りにされ、感謝され、認められる仕事は
より積極的にスキルやホスピタリティを
自主的に向上させる意欲まで育みます。
ある歯科医院では、
患者情報活用システムの導入から半年で、
スタッフの離職率が激減しました。
「ただの仕事」ではなく「患者の人生に関わる仕事」
という認識の変化が、スタッフのモチベーションを高めたのです。
別の医院では、情報活用の徹底により
ドタキャンや無断キャンセルが70%も減少。
「この医院、あのスタッフには迷惑をかけられない」という
患者側の意識変化が生まれた結果です。
このように、患者情報の活用は、
医院経営のあらゆる側面にポジティブな影響を与えます。
経済的にも恵まれ、労力は少なく、
そして何より充実感に満ちた歯科医院経営。
それが患者情報活用の先にある姿です。
情報活用への3Steps
では、具体的に何から始めればよいのでしょうか?
まずは、今日から情報収集の「型」を決めて、
スタッフ全員で共有することから始めましょう。
具体的には、以下の3ステップで進めることを
お勧めします。
Step1: 簡単なパーソナルシートを作成
A4用紙1枚程度でOK。
前述の5つの視点を含むシンプルなものを用意しましょう。
Step2: 明日から意識的に情報を収集
来院した患者から、受付や診療後の会話の中で自然に
パーソナルな話題を振って情報をさりげなく集め始めましょう。
Step3:ミーティングでの情報共有
週1回のスタッフミーティングで
得られた情報を共有してみましょう。
これは、特に重要な患者情報に絞ってで良いでしょう。
慣れてきたら、ピックアップの範囲を広げれば良いのです。
このシンプルな3ステップが、あなたの医院の
未来を大きく変える第一歩となります。
そして、3ヶ月後には、
患者の反応の変化を実感できるはずです。
患者情報の活用は、高額な設備投資や
特別なスキルを必要としません。
今日から、あなたの医院で実践できる
最も費用対効果の高い経営改善策の1つなのです。
ぜひ、明日からの診療に、
この「患者情報活用」を取り入れてみてください。
きっと、あなたの医院の風景が
少しずつ変わり始めることでしょう。