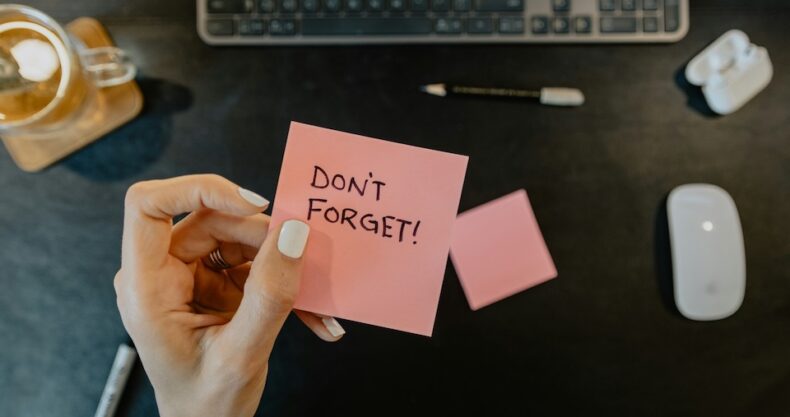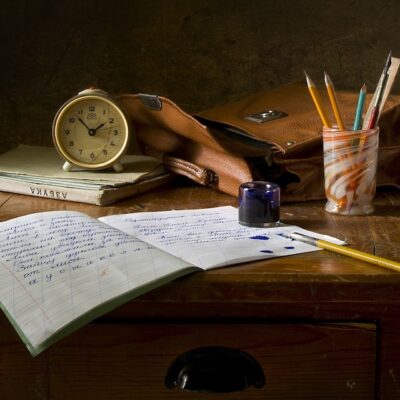臨床知識は27時間で70%消える?
これまでにも何回か、私のセミナーや
今回のような記事で紹介したことがあるのですが、
人間の脳は新しく得た知識や情報の約70%を
わずか27時間以内に忘れてしまうというのです。
先生は、こんな経験ありませんか?
熱心にメモを取った臨床セミナーの内容が
数日後には微妙に霞んでしまう…
高額な費用を払って参加した
hands-on 講習会のテクニックが、
いざ患者を前にするとうまく再現できない…
最新の治療メソッドが書かれた
専門書を一生懸命読んだのに、
実際の診療で活かせる部分がほんの一部だけ…
この現象は「エビングハウスの忘却曲線」と呼ばれ、
特殊な記憶力を持つ人以外は誰もが
経験する普遍的な脳のメカニズムです。
つまり、あなたがどれだけ優秀でも
この忘却のプロセスから逃れることはできないのです。
決して先生の努力不足や能力の問題ではありません。
ただし、この忘却曲線には「抜け道」があります。
ちょっとした工夫で「知識定着のメカニズム」が働き、
加速度的に忘却していくことを防げるようになるのです。
今日は、臨床知識やスキルを効率的に自分のものにする方法、
そしてそれを歯科医院経営にどう活かすかをお伝えします。
この記事を読むことで、先生の学びが無駄になる
時間とコストを大幅に削減できるはずです。
スキルと知識を定着させる48時間ルール
記憶の定着に関する研究で非常に興味深いデータがあります。
新しく学んだ知識やスキルは
「48時間以内にアウトプット」することで
記憶の定着率が劇的に向上するのです。
一部では「48時間ルール」と呼ばれています。
セミナーや論文から学んだ内容を
2日以内に何らかの形で表現する。
この単純なプロセスが、臨床スキルや診療スキルを
確実に自分のものにする鍵になります。
例えば、先日ある歯科医院の院長先生は
週末の臨床セミナーで学んだ内容を
月曜日のスタッフミーティングで
説明する時間を設けました。
「教えることは学ぶことの2倍身につく」
と言いますがまさにその通りで、
説明するために自分の中で知識を整理するので
その過程で理解が深まるのです。
また別の歯科医院の先生は、
新しい臨床のテクニックを学んだ後、
48時間以内に抜去歯で必ず実践するという
ルールを設けています。
このような「意図的な復習」により
セミナー参加費や学習時間の
投資効果を最大化できるのです。
では、具体的にどうすれば良いでしょうか?
一例を挙げてみましょう。
① セミナー当日または翌日に
5分でも良いので要点をまとめて書き出す② 診療室のホワイトボードに
新しく学んだポイントを箇条書きで貼り出す③ 新技術に関連する症例写真があれば整理して保存する
④ 48時間以内に同僚やスタッフに簡単にレクチャーする
⑤セミナー 翌日の診療で
1つでも応用できるポイントを意識的に実践する
重要なのは「完璧を目指さない」ことです。
5分でも10分でも、48時間以内に
何かしらのアウトプットをすることが
脳に「これは重要な情報だ」と認識させるのです。
この48時間ルールを
院長、スタッフ全員で実践した歯科医院では
研修費の実質的な効果が3倍に向上した例もあります。
最高の学びは、インプットだけでなく
適切なタイミングでのアウトプットにあるのです。
臨床知識・アイデア管理の方法
48時間ルールを実践するために
必要なのは「アイデアを逃さない仕組み」です。
歯科医師の先生方は日々の診療で
様々な気づきやひらめきを得ているはずです。
患者との会話から生まれたマーケティングのアイデア、
処置中に思いついた器具の使い方の工夫、
他のスタッフとのやり取りから浮かんだ改善策…
しかし、忙しい診療の合間に生まれた
これらの貴重なアイデアの多くは
記録されないまま消えていきます。
私が実際に見てきた成功例から
歯科医院で実践しやすい方法を
いくつかご紹介します。
実践法1. デジタルメモの活用
診療室の各ユニットにタブレットを設置し
気づいたことをすぐにメモできる
環境を作りましょう。
Google KeepやEvernoteなどの
クラウドメモアプリを使えば
後から検索も簡単です。
音声入力を活用すれば
入力時間のさらなる短縮も可能です。
あるインプラント治療に力を入れる歯科医院では、
術中の気づきを音声入力で記録し、後から
テキストの不備を修正する方法を採用しています。
実践法2. 診療後5分のリフレクション習慣
1日の診療終了後、あるいは昼休みに5分、
時間を設けて、その日の気づきや改善点を
ノートやデジタルツールに記録します。
この習慣を続けていた歯科医院では
半年後には貴重な臨床ノウハウの
宝庫ができあがっていました。
実践法3. 院内SNSやチャットの活用
SlackやLINE Worksなどのビジネスチャットを導入し
スタッフ間で気づきをシェアする文化を作ります。
「#臨床テクニック」「#患者対応」
などチャンネルを分けることで
情報が整理されていきます。
実践法4. 通勤時間の音声メモ
帰宅途中や通勤中に思いついたアイデアは
音声メモアプリに録音し後で文字に起こします。
車での移動が多い先生には特におすすめの方法です。
実践法5. 週一デジタル整理の時間
週に1度、30分程度の時間を取って
散らばったアイデアやメモを整理する時間を設けます。
月曜の朝一番や金曜の診療後など
定期的な時間を確保することが継続のコツです。
重要なのは「完璧なシステム」ではなく
「続けられるシステム」です。
成功している歯科医院の院長先生たちは
皆、自分なりのアイデア管理法を持っていました。
それは高度なITシステムではなく
日々の小さな習慣の積み重ねだったのです。
まずは今日から、先生のやりやすい方法で
アイデアを記録する習慣を始めてみてください。
経営と臨床を革新するヒント
さて、アイデアを集めることができたら
次のステップは「点と点を結ぶ」ことです。
蓄積した知識やメモを定期的に
全体を俯瞰するように眺めてみてください。
複数のアイデアが予想外の形でつながり、
思いがけない気づきが生まれることがあります。
これは私がコンサルティングの中で
「クロスリーディング」と呼んでいる方法です。
ある歯科医院では、集めたアイデアメモを
付箋で壁に貼り出して、週に一度、
院長とスタッフ全員で眺める時間を設けています。
そこから生まれたのが、
予防歯科の定期検診と季節のイベントを組み合わせた
マーケティング戦略でした。
別の事例では、歯周病治療のプロセスと
企業の品質管理の手法を掛け合わせて
治療効率を向上させた歯科医院もあります。
臨床知識とマーケティング、
患者心理と医院運営、
スタッフ教育と治療プロトコル…。
これらの異なる分野のアイデアが交わるところに、
他の歯科医院には真似できない
あなたの医院だけの強みが生まれるのです。
先日も、ある歯科医院の院長先生が集めていた
アイデアメモを一緒に眺めていた際に
「接客業のクレーム対応」と「難症例の説明方法」
を組み合わせた新しい患者説明の
フレームワークが生まれました。
それを実践した結果、自由診療の
成約率が1.43倍になったのです。
点と点を結ぶ発想法の実践には
「判断を保留する」姿勢が重要です。
「このアイデアは使えない」
「あの考えは非現実的だ」と
すぐに評価せず、まずは並べて眺める。
この単純な行為が、歯科医院に
革新的な変化をもたらす第一歩になります。
“臨床力”と”経営力”を高める知識活用術
これまでお伝えしてきた内容を
実践するための3ステップをまとめます。
STEP 1: 48時間以内のアウトプット
セミナーや勉強会で得た知識は
48時間以内に何らかの形で表現する。
メモでも、実践でも、誰かに説明でも構いません。
STEP 2: アイデア捕獲システムの構築
あなたの働き方にマッチした
アイデアを記録する仕組みを作る。
デジタルツールでも紙のノートでも、
続けられる方法を選びましょう。
音声入力を基本に選択することをお勧めします。
STEP 3: 定期的なクロスリーディング
集めたアイデアや知識を俯瞰して
新しいつながりを見つける時間を作る。
月に一度でも十分です。
この3ステップを実践した歯科医院は
例外なく臨床の質と経営の両面で成長を遂げています。
私自身も、この方法で
知見を整理し、活用しています。
最後に一つ、お約束してください。
「明日から一週間、この方法を試してみる」と。
知識の定着に特別な才能は必要ありません。
必要なのは、シンプルな仕組みと
それを続ける意志だけです。
あなたの歯科医院の未来を変えるのは
膨大な情報の中から何を選ぶかではなく
選んだ情報をいかに自分のものに
できるかにかかっています。
ぜひ明日から実践してみてください。